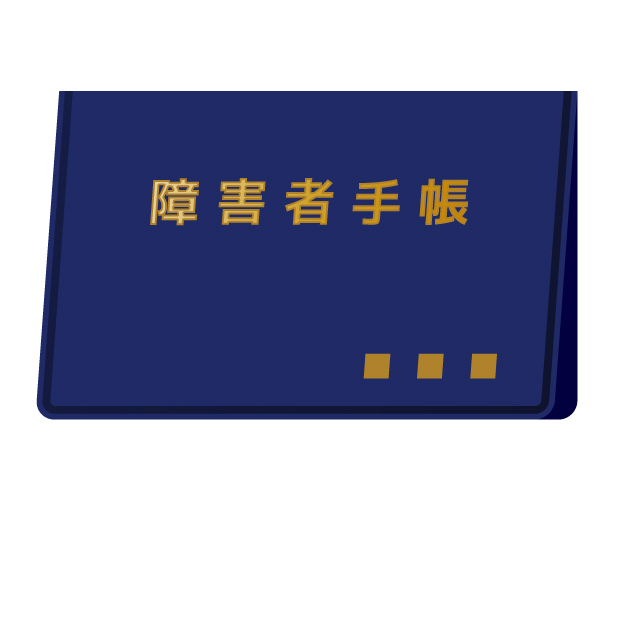福祉サービス
福祉サービス · 2023/01/02
自閉症の子どもが見ている日常生活の一部を五感で体験できるようにプログラムされています。
今までは、自閉症を頭の中では理解していましたが、VRを使うことによって体感し理解をさらに深めていただくためのきっかけになればと考えています。
今回、この『自閉症体験VR』をさらに多くの方に体験してもらうために機材やスタッフを派遣して体験会のお手伝いを行いたいと考えています。
対象はさまざまですが社会生活の一部として知っておくべき内容だと思います。
●幼稚園・保育園職員さんの研修教材
●小・中学校職員さんの研修会
●PTA関係者の研修
●保護者サークル活動の研修
●一般企業の研修会
詳しくはHPをご覧ください。
◉一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会ホームページ
https://www.ddsienn.jp/
◉お問い合わせフォーム
https://www.ddsienn.jp/contact/
自社が開催した『自閉症体験VR』の模様をNHKニュースで取り上げられていましたのでご覧ください。
福祉サービス · 2022/12/31
◉デメリットはなくメリットが多い障害者手帳
わが子の障害がわかったとき、親はそれぞれに葛藤があるかもしれませんが、 定期間が過ぎるとわが子の将来のために、親としてどのようなことをしたらいいか、前向きに考えるようになるのが一般的です。肢体不自由などの身体障害やダウン症などの知的障害の子の場合は早くから障害がわかるので専門職からアドバイスを受けて手帳の申請をするケースが多いでしょう。
ただ、知的な遅れの目立たない発達障害の子などの場合、親が障害を認められず、手帳を申請しなかったり、遅れたりすることも少なくありません。障害者手帳が将来わが子の不利益になるのではと心配する親も多いようです。しかし、手帳を取得することで、不利益になることはありません。一度手帳を取得してもとくに必要でなければ返すことができますし、手帳を取得していることを履歴書などに記載する義務もありません。
逆に、手帳をもっているメリットは少なくありません。子どもの成長とともに必要となる「教育」「就労支援」の分野でもサービスを受けるのに手帳の取得が条件になる場面が多いのです。さらに手帳を取得していることで各種の公的手当や税金の控除
福祉サービス · 2022/12/30
◉障害者手帳には3つの種類がある
わが国には、障害児 ・ 者の生きづらさを緩和し、いきいきとした暮らしを支援してくれる障害者福祉制度めに 定のハンディキャップがあることを証明するのが「障害者手帳」 制度です。数字、またはアルファベ ットで障害の程度を表していて、数字またはアルファベットの若いほうが障害の程度は重くなっています。
手帳を取得すると、わが子の特性に合わせた教育機関や就職の選択肢の幅が広がったり、各種の手当や割引 ・ 税金の控除など経済面での支援を受けることができるメリットがあります。
障害者手帳は身体・知的・精神の障害ごとに3つに分かれ、申請によ ってそれぞれの手帳を取得することができます。障害が重複する場合は、複数の手帳を取得することができます。申請方法は障害によって違いますが、それぞれの判定機関によって審議され交付が決定します。交付されるのは、身体障害では「身体障害 者手帳」、知的障害では「療育手帳」、精神の場合は「精神障害者保健福祉手帳」です。
福祉サービス · 2022/12/29
◉医療的ケアや訪問教育など柔軟に対応してくれる
学習が困難な子どもについては、各教科の内容の一部を取り扱わなかったり、下の学年の内容の一部または全部を代替したりと、個々の状態 に合わせた指導が行われます。
また、2つ以上の障害を併せ持つ子どもには、特例の措置として訪問教育が認められています。さらに、特別支援学校では、研修を受けた教員が、常駐している看護師と連携して特定の医療的ケアを行うことができるようになりました。
これにより、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内の痰の吸引や、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養が必要な子どもも、学校に通うことが可能になっています。
福祉サービス · 2022/12/28
特別支援学校は、かつて、盲学校、ろう学校、養護学校と区分されていた学校を一本化したもので基本的に障害の種別ごとに分かれていますが、都道府県によっては複数の障 害を1つの学校で受け入れているケースもあります。
幼稚部が併設されている特別支援学校もあり、小学部、中学部、高等部まで入学者は年々増加傾向にあります。
知的障害のある子ども以外は、通 常の学校に準ずる教科や道徳、特別 活動、総合的な学習の時間が組み込まれており、そのほかに、障害に基づく困難の改善・克服を目的とする自立活動の時間があるのが特徴です。
知的障害のある子どもの場合、自立活動はありますが、教科の内容を学年別に分けず、社会、理科、家庭科などを必修にするといった障害の 特性に合わせた授業が行われます。
福祉サービス · 2022/12/26
①通常学級と通級指導教室
地域の学校の通常のクラスで障害のない子といっしょに授業を受けながら、週に1 ~8時間、ほかの学校に設置された通級指導教室に通います。
対象となるのは、知的障害、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害などの子どもです。
障害の種別ごとに設けられた教室で、障害の程度に応じた授業を受けます。
ただ、通級指導教室に通うあいだ、 通常の授業を受けられないというデメリットがあり、文部科学省では通級指導教室の教員が障害のある子どものいる学校を巡回する(特別支援教室)構想を打ち立てました。
これにより、例えば東京都では、発達障害や情緒障害のある子を対象にした特別支援教室をすべての公立小学校に導入しています。